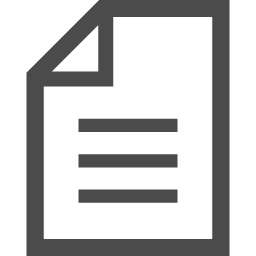障害が起きた時には、緊急対応すべきものと恒久的な対応として実施すべきものがある。
障害時の心得を学ぶ機会があった。
自分の中では理解できていたつもりになっていたけど、いざという時に動けるように身で覚えておかないと。
未来を考える前に今すべきことをしろ。
怪我をしたなら、まず怪我を治せ。
漢方薬を飲んでる暇なんかない。
まずは、すぐに傷口をふさぐこと。
恒久的な対応ばかりを意識していては、傷口は拡がるばかり。
まずは、暫定対応でも良いので悪い状況をどうにか改善、解決すること。
暫定対応を行っておけば、恒久対応について考える時間を作ることができる。
緊急時は同時に並行で動け。。
火事の場合は、報告と避難と消火を同時にする
そういえば避難訓練をする時も、消防署への連絡や消化班による初期消火作業、誘導班による避難の実施など並行で動いていた。
自分はシングルタスクでしか物事を考えていなかった。
緊急を要する場合には複数同時に行動を起こす必要がある。
1人で同時対応が無理であるなら、仲間を使えばいいだけのこと。
当たり前のことなら、プロセスやルールを増やす必要はない。
どうしても、障害対応後の是正計画や恒久対応の方法としてはプロセスやルールを増やす方向にもっていきがち。
それは自分たちを余計に苦しめることになることが多い。
青信号で横断歩道を渡ること、道路を渡るときは左右を見る。
子供ならともかく、大人であれば当たり前の行動。
いちいち文書に残す、毎回確認するのは時間の無駄。
わかりやすい事象で考えろ。
迷ったら、現実のノウハウを活かすこと。
怪我の話も火事の話、横断歩道の話も現実に置き換えれば自然と、その時に行うべき行動が見えてくる。
もちろん、障害は起きないにこしたこと無いんだけど。
常日頃から、こんな時はどうすべきなのかと考えておくことが大事。